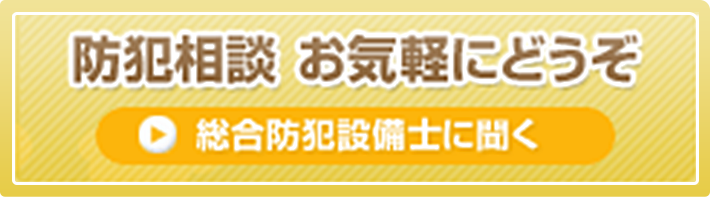今日巷で話題の犯罪について防犯のプロが語る
文化財・寺社への放火相次ぐ
全国で文化財や寺社の火災・放火が多発しています。
●白沙村荘茶室を全焼 左京・橋本関雪の旧宅。出火時は無人
31日午前1時ごろ、京都市左京区浄土寺石橋町の白沙村荘・橋本関雪記念館から出火、木造平屋の茶室(約120平方メートル)を全焼し、約20分後に消した。 茶室は、関雪が1932年ごろ妻のために造った「倚翠亭」や「憩寂庵」の2つで、出火当時茶室はいずれも無人だったという。
(3月31日 京都新聞より抜粋)
●小田原市江之浦の「赤沢観音堂」から出火・放火の疑い。仏像4体も焼ける。
29日午前10時50分ごろ、小田原市江之浦の「赤沢観音堂」から出火、木造平屋約50平方メートルを全焼し、内部にあった十一面観音像など仏像4体を焼いた。約6時間後、住所不定、無職の男(57)がJR真鶴駅前の交番に「火をつけた」と自首したため、小田原署は非現住建造物等放火の疑いで緊急逮捕した。出火約1時間前、参拝者が施錠されたはずの堂内で50〜60歳代の不審な男を目撃。同署は特徴が似ていることからこの男とみており、動機などを追及している。
(3月30日 毎日新聞より抜粋)
●国宝火災:奈良の出雲建雄神社拝殿に放火か 格子戸焦げる
12日午前4時半ごろ、奈良県天理市布留(ふる)町にある石上(いそのかみ)神宮の摂社・出雲(いづも)建雄(たけお)神社拝殿(国宝)から出火。火災報知機で気付いた神社当直の男性権祢宜(ごんねぎ)(32)が消火器で消し止めたが、格子戸など7カ所が焼け焦げた。権祢宜は「油のにおいがした」と話しているといい、県警天理署は放火の疑いが強いとみて捜査している。
山辺広域行政事務組合消防本部によると、拝殿の外周を囲むように7カ所に油がまかれていた。拝殿東側にある別の社付近で、油の入った瓶とライターが見つかったという。
消火後、拝殿の敷居や土壁も焦げていることが分かった。
(3月12日 毎日新聞より抜粋)
それ以外にも、
●22日午前6時ごろ、神奈川県大磯町西小磯の旧吉田茂邸から出火。午後零時半すぎに鎮火したが、木造2階建て本邸約1000平方メートルを全焼した。
●15日に国の重要文化財「旧住友家俣野別邸」(横浜市戸塚区)が全焼している。
日本の文化財や寺社はほとんどが木造のため、火災や放火が一旦発生すると消失するものは計り知れません。
これだけ多くの重要文化財や寺社が全国で火災や放火が発生しているというのは、偶然ではなく、ニュースで見た事件を真似たのではないかと私は推測しています。
放火をする人間の心理は、「むしゃくしゃして」といったストレス解消犯や、皆がバタバタして消火活動しているのが面白いといった愉快犯、スリルを愉しむといったものがあります。
いずれにしても社会の不況や閉塞感などに負けた弱い心が行う最も卑怯な犯罪の一つだと思います。
そんな放火被害に遭わないためには、
1)敷地内に不審者を入れないこと。
2)周囲に放火しやすいものを放置しないこと。
3)夜間も明るく死角を作らない。
4)放火をいち早く検知し初期対応すること。
があります。
1)敷地内に不審者を入れないこと。
赤外線センサーなどで外周警備を実施し、不審者がフェンスを越えたり、塀をよじ登ったり、敷地内に侵入した時点でベルやサイレンで威嚇撃退する。
2)周囲に放火されやすいものを放置しないこと。
段ボール箱、ゴミ、古新聞、古雑誌、木材などが敷地内に放置されたままであるとそういうところに放火される可能性があります。寺社では納札所や絵馬などが狙われやすいので注意が必要です。
3)夜間も明るく死角を作らない。
夜間暗闇の中に姿を隠すことができるのは犯人には好都合。防犯灯や人感ライトなどで周囲を明るくし死角を無くすことで犯罪者が犯行しにくい環境が作れます。
4)放火をいち早く検知し初期対応すること。
火災感知器では温度の上昇を検知する方式のためある程度の火の手が上がってから検知することになります。木造建物の場合はそれでは遅いので、放火の危険がある場所には炎センサーを設置することをお勧めします。炎センサーは10メートル先の7センチの炎を検知、音声メッセージでその場で警告したり離れた管理者に連絡することができます。
外周警備の赤外線センサーやや放火検知の炎センサーなどは防犯カメラと連動し、異常発生時の映像を自動録画するとともに、離れた場所にいる管理者の携帯電話に自動通報すると動画で現場状況を把握しながら初期対応ができ、より安心です。
見える自主機械警備システム
寺社の放火対策
投稿者: スタッフ (2009年3月31日 09:19)
ワイドショー見て17歳が「自分も」 泥棒を実行
TVなどで犯罪手口を見て、それを真似して犯行を行う、というのはよくあります。
福岡の17歳の少年がTVのワイドショーを見て泥棒を実行、その後も犯行を繰り返していました。
福岡県警中央署は27日、福岡市で店舗兼住居を狙って盗みを繰り返したとして、同市博多区の無職少年(17)を窃盗容疑で逮捕したと発表した。
「テレビのワイドショーを見て自分にもできると思った。店の営業中には住居に人がいないので、犯行しやすいと思った」と供述しているという。
発表によると、少年は1月26日昼頃、同市中央区清川2の飲食店兼住宅の2階住宅部分に無施錠の窓から侵入。約38万円などを盗んだ疑い。
犯行前には1階の飲食店で食事し、居住者を確認。<strong>雨どいをつたって2階まで上がったという。
犯行後、署員が脚立を持っていた少年を見つけて職務質問。犯行現場に残された掌紋と一致したため2月に逮捕された。
同署は昨年12月18日から今年1月26日までに、逮捕容疑を含め窃盗など計15件(被害総額360万円)の犯行を重ねていたことを確認したという。
(3月28日 読売新聞より引用)
この少年はTVを見て真似たようですが、その手口は思いつきではなく非常に計画的な犯行です。
● 住居併用型店舗を狙う。理由は昼間の営業中住居部分は無人であるため。
● 先に店舗に行って住居部分が無人かどうか確認(下見)
● 2階の住居部分に雨どいをつたって近づく。脚立も使用。
● 2階部分の無施錠の窓から侵入。
と泥棒の原理原則をきちんと押さえています。
泥棒にとっては「下見」をして「侵入しやすいかどうか」「人目につかずに安全に犯行を終えることができるか」などを確認して犯行対象を絞ります。
不在確認は空き巣の場合はインターホンを押す、電話をかけるなどですが、住居併用型店舗の場合は店舗にわざわざ行って確認しています。
こうした住居併用型店舗の場合、「常に人がいるから防犯対策はいらない」と思われる方が多いのですが逆です。
常に人がいるから泥棒と鉢合わせになる可能性が高く人命が危険にさらされるのです。
最も大切な家族の命が危険にさらされているのだということを認識して欲しいです。
防犯対策としては「在宅警備」「部分警戒」がきちんとできる防犯システムを設置する必要があります。
●人が常にいる場所以外は警備を実施する。
●昼間でも窓からの侵入者はきちんと警報ベルを鳴らす。
●外出や旅行など完全に無人になる時には離れた場所で異常発生を知り初期対応ができるようにする。
こういう防犯システムを設置することで昼間も夜も安心して生活や商売を行うことができます。
店舗の防犯対策
投稿者: スタッフ (2009年3月30日 11:36)
ひったくり急増。犯罪者が振り込め詐欺からひったくりに変更か?
「振り込め詐欺」から「ひったくり」へ・・。ちょっと気になる傾向が出ています。
東京都内で今年、ひったくり被害が急増して被害件数は600件を超え、前年同期に比べて約36%増となっていることが26日、警視庁のまとめで分かった。
不況から経済的に追いつめられ、特殊な道具や技術を必要としないひったくりの増加につながっているとみられるが、「振り込め詐欺が摘発強化されたことで、犯罪者がひったくりに流れている」と分析する専門家もいる。世界的な経済危機の出口が見えない状況下で、さらに続発する可能性もあり、同庁で警戒を強めている。
■敷居の低さ
警視庁捜査3課によると、ひったくり被害は24日現在で672件となり、前年同期に比べて180件、約36%増となった。昨年12月から増加傾向にあるという。このうち9件は被害者が転倒して負傷したため、強盗致傷事件となっている。全体の約7割ではバイクが犯行に使われていた。
一方でほかの窃盗被害は空き巣などの侵入窃盗が前年同期比305件減の2628件▽車上狙いが331件減の1758件▽自動車盗が72件減の136件−と減少している。
捜査幹部は「ほかの窃盗は工具や技術、経験が必要になるが、ひったくりはバイクや自転車があればできる」と指摘し、ひったくりの“敷居の低さ”を説明する。
立正大学の小宮信夫教授(犯罪社会学)は「失業者が増えるとひったくりも増えるが、振り込め詐欺の摘発強化も背景にあるのではないか」との見方を示す。
警視庁は振り込め詐欺対策として、だまし取った金を現金自動預払機(ATM)から引き出す「出し子」の顔写真をホームページで公開、ATM周辺に写真を掲示するなどして摘発に力を入れている。
同庁によると、振り込め詐欺撲滅月間の2月、都内の振り込め詐欺被害は72件、約1億4000万円となり、統計を取り始めた平成17年1月以降、過去最少だった。
小宮教授は「振り込め詐欺の逮捕のリスクが高まった。犯罪者はバイクや自転車で追い抜きざまに荷物を盗むひったくりの方が、リスクが低く、手間もかからないと感じ、手を出すようになったのではないか」と分析する。
■狙いは弱者
同庁は24日現在でひったくり事件の容疑者37人を逮捕しているが、供述から、「犯行後に追いつかれない」「抵抗されない」という理由から女性や高齢者といった弱者を狙っていることが浮き彫りになった。
同課によると、バイクを使って自転車の前かごからバッグをひったくったとして、今月4日に窃盗容疑で逮捕された男は体重125キロの巨漢だったが、「自分が乗ったバイクはスピードが遅くなってしまうので、自転車をこぐ力が強い男性は狙わなかった」と供述している。
同課はひったくり被害を防ぐ手段として、歩くときは建物や壁側の方でバッグを持つ▽自転車のかごに荷物を入れる際には、かごにネットをつける▽背後から自転車やバイクの音が聞こえたら振り返る−の3点を挙げている。
小宮教授は「ひったくり犯は幹線道路の近くにあるガードレールのない道や、高い塀が続く道など『入りやすく見えにくい場所』で犯行に及ぶ。このような場所では特に注意が必要だ。ひったくり犯はリスクを嫌がるため、危険な道路でも通行人が警戒心をアピールしていればあきらめる」とアドバイスしている。
(3月27日産経新聞より引用)
小宮教授の「犯罪機会論」は「防犯環境設計」の考え方にもなっています。
偶然ですが、セキュリティハウスの「予防(抑止)」を強化する自主機械警備システムの考え方とも非常によく似ています。
犯罪者に犯罪をしにくい環境を作ることで犯罪対象から外させる。
そのために建物外に「抑止機器」を設置し、犯罪者に精神的な抑止を行う。
建物内に入られる前に音と光、人の目という「侵入防止4原則」を活用して威嚇撃退する。
それがセキュリティハウスの自主機械警備システムの考え方です。
ひったくりに関しては、
ひったくりに対する防犯対策を参照下さい。
投稿者: スタッフ (2009年3月27日 11:01)
あなたのスーツケースが危ない! 年間126万個が紛失。
海外旅行時に一番頭を悩ませるのは自分の荷物に関して。
団体旅行なら全て添乗員任せですが、個人旅行となると航空会社に預けて、無事受け取って、ホテルに移動して・・といったことをすべて自分でやらなければならず、その安全性に関しては結構神経を使います。
J-CASTニュースにちょっとびっくりするようなスーツケースの紛失・盗難の被害に関して掲載されていましたのでご紹介します。(以下ニュースの抜粋)
旅客機に乗る時に預けたスーツケースなどの手荷物が、1年間に全世界で4200万個紛失し、うち126万個が見つからず、38億米ドルの損害賠償請求が出されている――こんな衝撃のレポートが、ヨーロッパに拠点を置くコンサルタント会社から出された。なぜこんなことになってしまうのか。
■欧州では300人乗り旅客機で常時5人が被害
旅客機の手荷物に関するレポート「Baggage Report 2008」を出したのは、世界220ヵ国で旅客機の手荷物状況をインターネットリサーチしている「SITA」(シータ)。それによると、航空機会社が預かった手荷物のうち、2007年には4200万個のバッグが行方不明になった。05年は3000万個、06年は3400万個と年々増えていて、このままでは旅客機利用者の増加に比例し10年後の19年には7000万個が失われるだろう、と予想している。無くなった手荷物の大半は48時間以内に見つかるのだが、07年は126万個が完全に紛失した。
しかし、航空関係職員が手荷物を積み忘れたり、逆に降ろし忘れたり、引き渡し場所を誤るなど様々な原因が考えられるが、それにしても126万個が完全紛失、というのは驚きだ。
日本でも航空機会社に預けた手荷物の紛失が増えているのだろか。全日空広報は、
「日本の航空会社の場合は荷物を紛失する、などということはめったにありません。ましてや完全に無くしてしまうなどというのは考えられません。全てコンピュータ管理していますので、一時的に見失ったとしてもすぐに見つかる仕組みになっています」
と説明する。
ある航空関係者はJ-CASTニュースに、荷物の紛失は乗り換えの際に多発している、と打ち明ける。特に多いのがヨーロッパ。例えば300人乗りのジェット機の場合、1回の飛行で平均して5人の荷物が無くなる状況なのだという。
■「貴重品は預けずに身近で管理した方がいい」
これは、違う会社の旅客機に荷物を積み替える際に多く起こるトラブルで、コンピュータ管理ではなく、積み荷表などを見てマニュアルで積み替えする場合に生じる。ただし、そんなケアレスミスのようなものばかりではないらしい。飛行場で働いている職員が、計画的に盗みを働くことが増えているというのだ。
パリのドゴール空港で、荷物運搬係が空港利用客のトランクなどから金品を盗み、逮捕された、というニュースが08年10月2日付けの西日本新聞に掲載された。逮捕された12人は同じ空港サービス会社の社員。盗んだ中身は宝石、トラベラーズ・チェック、パソコン、高級靴など多岐にわたり、その一部をネットオークションで売りさばいていたという。同空港では同様の組織的窃盗が常態化していて、「ターミナル2」だけで、07年の盗難届は621件。逮捕された元荷物運搬係は裁判で「係のみんなが盗んでいる」と証言している、という。
パリのドゴール空港は巨大で乗り換えるためにターミナル間を移動するだけで1時間近くかかります。
スケジュール上は2時間ほど次のフライトまでありましたが飛行機到着が遅れ、移動時間がほとんどなく小走りに移動しました。
まして荷物となるとなかなかうまくいかず、良く荷物の積み遅れが発生しています。
という私も昨年の7月 リスボンから乗り換え関空に乗ったところ、トランクだけが翌日便になっていました。幸い関空に到着した時点で連絡が入っており、関空にいる日本人スタッフから翌日到着後運送便で自宅に送ってもらえるとの内容を確認できたので安心しました。(但し、余計に日数がかかったためか?トランク内のチョコレートが解けかけて一部お土産が駄目になりました)
ヨーロッパではトランクのラッピングサービスも見かけます。
ミイラのようにぐるぐる巻きにサランラップをかけるのですが、やはり盗難防止が目的ということで、頻繁にそうした被害があることを裏付けています。
私の友人は英国から日本に戻ったときに、トランク内の貴金属を全て盗まれるという被害に遭いました。
やはり貴重品は絶対に手荷物として飛行機に中に持ち込み自分自身で管理することが必要です。
又、できる限り乗り換えがある場合には時間に余裕を持たせたフライトを選ぶことも大切です。
2時間も・・とスケジュールを考える時には思うかもしれませんが、国際便の2時間は余裕とはいえないと考え行動すべきです。
鍵はアメリカ便はかけれませんが、それ以外では厳重に施錠し、ベルトもしっかり締めて簡単にはこじ開けられないよう時間がかかるようにするべきです。
投稿者: スタッフ (2009年3月26日 13:35)
社会福祉施設・文化財建造物ともに火災対策が急務
全国で火災被害が相次いでいます。
●19日群馬県渋川市の高齢者施設「静養ホームたまゆら」で入所者ら10人が死亡した。職員は1名で、スプリンクラ−の設置もなく、火災保険も切れており、通路にある引き戸にはつっかい棒をかけて、(入居者が)外に出ないようにしていた、という劣悪な環境であった。禁煙にもかかわらず喫煙をしている入居者もおり長年暗黙の了解となっていた。「タバコの不始末」が原因と見られる。
●22日午前6時ごろ、神奈川県大磯町西小磯の旧吉田茂邸から出火。午後零時半すぎに鎮火したが、木造2階建て本邸約1000平方メートルを全焼した。けが人はなかった。県警大磯署は失火と放火の両面で調べている。旧吉田邸の敷地内には24時間態勢で警備員が常駐、22日午前5時半すぎ、敷地内の巡回点検を終えた警備員が警備室に戻ったところ、漏電警報が鳴った。約20メートル離れた本邸に駆け付けると、2階から煙が出ていた。2階部分が激しく燃えており、同署は2階が火元の可能性があるとみている。その際、2カ所ある入り口はどちらも施錠されていた。火災報知機や監視カメラ、侵入者を検知するセンサーはなかった
●神奈川県内では、15日に国の重要文化財「旧住友家俣野別邸」(横浜市戸塚区)が全焼している。
また、昭和初期の洋館「旧モーガン邸」(藤沢市)でも2007年5月と08年1月、本棟と別棟をそれぞれ全焼する火災があった。旧住友家の出火原因は分かっておらず、旧モーガン邸については県警が放火とみて捜査している。
旧吉田邸は県立公園として保存する計画が進められていながら、国の重要文化財(重文)に指定されていないため、特別な防火対策は講じる義務はなかった。邸内の防火設備は漏電警報器と消火器だけ。重文であれば消防法によって自動火災報知設備と消火器の設置が義務付けられ、放水銃や貯水槽などの設置も促されるが、西武鉄道は「重文ではないので一般の民家と同じ扱いでいいという認識。行政から防火設備の指導を受けたこともない」と説明する。
文化庁はあくまで「重文以外の建物を指導することはない」という立場。防火設備の金銭的負担のほか、建物の増改築が許可制になるなど制限が生まれるため、同庁によると所有者が重文指定を避けるケースもあるという。
重文指定を受けていない建造物は、いわば保護行政の"死角"。では、重文以外で歴史的な価値が認められる建造物をどう守るべきなのか。都市・建築の防災に詳しい東大大学院の関沢愛特任教授は「神社仏閣では内部に手を加えることは難しいが、近代的な建物の場合、スプリンクラーの設置が比較的容易にでき、金銭的負担も少なくて済む」と指摘。具体的には「歴史的建造物を美術館などに転用する活用保存による防火対策が有効。重文指定も含め文化財の保護行政にはもっと柔軟な発想が必要だ」と訴える。
一方で立命館大の土岐憲三教授は文化財建造物への放火が後を絶たないことから、「不審者感知のセンサーの設置など火災を未然に防ぐ対策が必要だ」と強調。県内でも「旧モーガン邸」「旧住友家俣野別邸」の焼失が相次いでいる。横浜市は「いずれも不審火の可能性がある」として改修工事中の「旧伊藤博文金沢別邸」(金沢区)に夜間、警備員を常駐させる対策を取っている。
火災を受け、総務省消防庁と国土交通省は23日、社会福祉施設を緊急点検するよう全国の消防本部などに要請した。火気管理や避難経路の確保などを重点的に調べ、違反があった場合には直ちに是正させる。
同庁はまた、神奈川県大磯町の旧吉田邸全焼火災などを受け、全国の文化財建造物を対象とした緊急点検も要請。防火対策の現状を把握するほか、防犯カメラの設置や敷地内への入場管理の徹底などを求める。
(3月23日時事通信、カナロコより一部引用)
火災は発生すると人命はもちろんのこと、歴史的な価値も、文化財も何もかも灰と化してしまいます。
そういう火災の原因としては、
● 放火
● 失火
● 漏電
などがあります。
「放火」「放火の疑い」という原因での火災発生がもっとも多く、この「放火対策」を十分に行うことこそ火災被害から身を守ることになります。
「放火」を防ぐためには、
● 不審者を敷地内に入れさせない。・・・赤外線センサーによる外周警備で不審者を音と光で威嚇撃退、人感ライトや防犯灯の追加、フェンスなどによる境界線の明確化。
● 不審者に「放火」させるものを提供しない。・・雑誌・新聞・ダンボール箱など燃えやすいものを屋外に放置しない。
● 犯行を早期発見する。・・・炎センサーで10メートル先の7cmの炎を検知し、音声威嚇。防犯カメラで炎の発生や不審者侵入を画像で確認・自動録画。異常発生を離れた場所にいる管理者のFOMA携帯電話に画像通報・動画で状況把握し、早期対応。
● 老人保健施設などでは119番自動通報装置などを設置し、押しボタンを押すと119番に自動通報する。徘徊防止は施錠やつっかい棒ではなく、電気錠を使用し、通常は徘徊者のみ施錠、職員・入居者は自由に出入り可能・火災発生時には自動的に開錠するシステムを導入する。
こうした物理的な防火対策に加えて、防火責任者を設置し、常に防火時の対応に関して関係者と協議する、消火器、火災感知器、スプリンクラーなど防火対策機器の定期点検、防火訓練などを実施するといったソフト面の防火対策も徹底して実施することが大切です。
被害が発生している建物の中には、何も防火対策もされず、防火訓練もしていないところや、施錠やつっかい棒で外に出れない状況のままのところも多かったのが印象に残ります。
火災の被害が大きくなるか、ボヤなど最小で押さえることができるかは、そこを管理する人間の防火対策やリスクに対する常日頃からの認識により大きく左右されます。
「法律に縛られていないからなにも対策をしない」という考えでは被害を防ぐことはできません。
どこも予算は厳しいでしょうが、失ってからでは遅すぎるのであるということを、高齢者施設「静養ホームたまゆら」や旧吉田邸の無残な焼け跡が教えてくれます。
この教訓を関係者は活かしていただきたいと願います。
文化財・老人保健施設・寺の放火対策
投稿者: スタッフ (2009年3月25日 09:35)
公園の砂場に注射針80本散乱。
誰が何の目的で行ったのでしょうか?
24日午前6時55分頃、兵庫県尼崎市塚口本町の塚口第2公園で、砂場(約4メートル四方)内やブランコなどの遊具周辺に、注射用とみられる針約80本が散乱しているのを、近くの男性(66)が見つけ、110番しました。
尼崎北署はいたずら目的でまかれた可能性もあるとみて、軽犯罪法違反容疑で調べています。
同署の発表によると、針は、長さ3センチと2センチの2種類で、インスリンや血糖値測定用とみられる。公園は市が管理しているが、前日の午前9時頃に担当者が清掃した際には異状はなかったということです。
(3月24日読売新聞)
子供たちが遊ぶ公園の砂場に注射針をまく。
なんと悪意に満ちた行為でしょうか。
なにもなく、大人が見つけることができて本当に良かったです。
この公園に防犯カメラが設置されていたとの記載はありませんでしたので、設置はないのかもしれません。
公園の防犯対策に関して、市町村でも見直しを進めています。
見通しの良い公園。大人が子供たちの様子を見守ることができること。
そのためには
●公園の立地(道路からの死角をなくす)
●夜間照明の追加
●植木の剪定・雑草の削除
●遊具道具の配置場所の見直し
●遊具道具そのものの安全性
●公衆トイレ内の安全性のアップ(緊急押しボタン)
●防犯カメラの設置
子供たちが安心して遊べる公園になるよう大人が連動して実施することが重要です。
又、針の盗難などが発生しないように、病院・医院などは、新品の針の盗難防止はもとより、使用済みの針の保管を徹底し、防犯対策として敷地内に不審者が侵入した時点で威嚇撃退できるような防犯システムを設置することをお勧めします。
投稿者: スタッフ (2009年3月24日 16:28)
トラック窃盗団
現在の泥棒はお金に換金できる物なら何でも盗みます。
パソコンも仏像も、金属も「換金できる」ことで泥棒のターゲットになっています。
泥棒が盗むものは隠せるほど小さいものかというとそうでもなく、大きなものでは「トラック」。
トラックばかりを狙う「トラック窃盗団」もあるのです。
運送会社をターゲットにしたトラック窃盗団。
運送会社の駐車場からトラックを盗んだとして、埼玉県警捜査3課などは23日、千葉市中央区矢作町の無職A(33)=窃盗罪で公判中=ら4人を窃盗容疑で逮捕したと発表した。捜査3課によると、昨年2〜11月に埼玉、千葉県で約130台(約1億3000万円相当)の被害を確認したという。
逮捕容疑は、4人は昨年8月26日夜、千葉市若葉区の駐車場で、トラック4台(80万円相当)を盗んだなどとしている。捜査3課によると、容疑者らは容疑を認め、「千葉市内で車の中古品を扱っていた40代のウガンダ国籍の男に1台20万〜30万円で売った」などと供述しているという。
(3月24日 毎日新聞より引用)
運送会社などでは、トラックそのものが盗まれる他、ミラーやバンパーなどトラックの備品が盗まれる被害が多発しています。
考えてみてください。
何百万もの備品を屋外に置いている状態ということですから、トラックやその備品が現金に換金できるとなると狙われるのは必然といえます。
実際に盗まれたトラックや備品は海外に販売されます。
運送会社ではミラーが盗まれただけでもその日そのトラックは使用できません。
「予約の入っている仕事に穴を開けることになる」
これは本当に大変なことで、ミラーだけの被害ではないのです。
そうした被害を防ぐには、敷地内に侵入した不審者をその場で威嚇撃退する外周警備システムと、防犯カメラの映像を携帯電話に動画通報する「見える自主機械警備システム」が好評です。
先日もTV取材で、滋賀県の運送会社様が紹介されました。
「設置後、被害はまったくなくなった。ゼロ。」と力強い言葉を頂戴しました。
スーパーJチャンネル映像
投稿者: スタッフ (2009年3月24日 13:53)
チリ人おしっこドロボー団
チリ人おしっこドロボー団!ちょっと汚い手口です。
警視庁捜査3課に逮捕されたチリ人男性3人。
東京都台東区の銀行で女性客に尿と見られる液体をかけ、注意をそらして現金を盗もうとしました。
同課によると、昨年末から港区と中央区で中南米系の男らによるとみられる手口の窃盗事件が4件(被害総額約840万円)あり、容疑者らが関与したと見て、調べを進めています。
18日午後零時半ごろ、現金30万円を引き出した会社員の女性(62)を取り囲み、化粧品用のプラスチックケースに入った黄色い液体をかけ、現金を盗もうとした疑い。
容疑者らは女性の背後から忍び寄り、尿をかけ、驚いたスキを狙い、現金の入った書類ケースを盗もうとしたが、途中で女性に気付かれ、張り込んでいた捜査員に現行犯逮捕されました。
捜査員は港区内で3人を見つけ、台東区まで尾行していました。
元警視庁刑事の北芝健氏によると、金融機関などから現金を持ち帰る途中の人に狙いをつけ、現金を持ち去る犯罪者のことを、警察では「途中狙い」と呼んでいるということです。
世界各国共通する手口らしく、特に中東や南米で横行し、銀行、両替所、ブランド店から出てきた人を狙います。尿をかけるのと同様に、複数人での犯行が多く、女性がつまずき、男性の服に口紅やアイスクリームをつけ、一緒にいた男性が「服をきれいにします」などといい、服を脱がせ、逃走する手口が多いという。また、両替所を出てきたところに「偽札の疑いがある」と声をかけ、お金を出させ、疑われた場合は途中で断念し、別の警察を名乗る犯人が声をかけ、信用させる“二重のワナ”を仕掛けてくる手口もあるということです。
(3月20日スポーツ報知より抜粋)
複数名の人間が役割分担してお金を盗む、というところは「振り込め詐欺」と同様です。
振り込め詐欺は、「いかに信用させ、お金をすぐに振り込まないといけない」と思い込ませるか、が目的となって何名もが演技をしますが、
「途中狙い」や「ひったくり」「スリ」などは、「いかに気を他の方に向けるか」ということを考え、夫々の役割の人間が演技を行います。
ケチャップを付けたり、ソフトクリームを付けたり、お金を目の前でばら撒いたり、倒れたり・・・。
自動車に乗っているときも、ぶつかってきたり、目の前で事故を起こしたりして他のことに気が向いて隙ができた瞬間、別の人間がカバンや貴重品を持ち去るのです。
銀行や両替から出てきた時、又入ろうとする時周囲に目を凝らして、自分を注視している目がないか気にかけることも必要です。
海外の場合、銀行の中に入るにはカバンをロッカーに入れて、一人づつゲートを通るなど銀行に入ることが非常に厳しいところも多いです。
両替の場合は、かなりいかがわしい感じの民間の両替商もいます。
大きな文字で両替レートが記入されているのですがそれ以外に手数料が非常に多く、??といった金額しか両替されないこともありました。現地の言語に通じていないとトラぶった時に通じないということもありますので、注意が必要です。
一度両替商から出てくる時に、お金を戻しながら出てきてしまい、変な男に話し掛けられたことがあります。そういう風に知らない人が突然話し掛けてきた時は注意が必要です。
外国ごとに犯罪の傾向や手口も異なりますので外務省のホームページや弊社の海外での防犯対策ページをご確認下さい。
投稿者: スタッフ (2009年3月23日 10:10)
大分 野焼きで高齢者4名死亡
70代以上の男女4人が犠牲になった大分県・湯布院町の野焼き事故。熊本県の阿蘇山のすそ野や北九州市の平尾台で行われる野焼きに携わる関係者からは、作業の危険性とともに、人手不足のため高齢者が作業を担わざるを得ない現状を懸念する声も聞かれた。
●死亡した4人のうち宮本義広さん(75)=同市湯布院町塚原=以外の3人は現場での野焼きに参加するのは初めてだった。
●野焼きは昨年まで事故現場を含む2地区で同時に行っていたが、参加者の高齢化で人手が足りず、今年は午前と午後に1地区ずつ実施。宮本さんを除く3人は、昨年まで別のもう1つの地区を担当し、事故が起きた地区は初めてだった。慣れない場所だと、火の走り方が分かりにくい。
●亡くなった4人は防火帯(幅約8メートル)の外に燃え移った際に火を消す役割だったが、遺体が見つかったのは防火帯などに囲まれた野焼きのエリア(約30ヘクタール)内。2人は東側の谷付近で、別の2人は西側の山頂から中腹にかけて見つかった。4人の遺体は20‐200メートル離れていた。なぜ4人が防火帯の内側に入ったかについて、地元消防団の1人は「予定以外の場所に火が広がってしまい、消そうとして近道をしたのではないか」とみている。
●乾燥注意報下での野焼きが恒常的に実施されていた。県内全域に注意報が発令されているのを知りながら、野焼きの実施を黙認した市の安全管理に問題があった可能性もある。
慣れない野焼きで想像以上に火の回りが早く、逃げられなかったということだと思います。亡くなった4名はいずれも高齢ですから逃げる体力も途中からなくなってしまったのかもしれません。
ただ、こうしたことがあると、ボランティア団体や組合などで実施しようとする人がいなくなるのではないかと少々気がかりです。
大分だけでなく多くの地域で野焼きは実施されていますが、いずれも高齢者が中心で実施せざるを得なく、又命がけの作業という面は避けられません。
いずれにしても、今後は今回を教訓により一層の注意が必要です。
注意点/
●風速などの気象条件を考慮。乾燥注意報が出ている時には実施しない。
●あらかじめ焼く部分と焼かない部分を分ける防火帯をつくり、点火場所や焼く方向など綿密な計画が必要。
●参加者には研修を実施し、初めての参加者には必ずベテランがペアで行動する。
●消防署、消防団のほか、自衛隊にも協力を依頼、5‐6人のグループに1人の割合で無線を所持した自衛隊員に同行してもらい、点火時などの連絡態勢を強化する。
●単独行動をしない。
●未燃焼部分に立ち入らない。
●入っても、常に退路を確認しておく。
( 3月18西日本新聞より一部引用)
投稿者: スタッフ (2009年3月19日 10:17)
ゴルフクラブ41本盗み売却…「生活のため」
愛知県警で逮捕された住所不定、無職男(55)。
昨年12月末、名古屋市中区千代田、不動産賃貸業の女性(52)方の駐車場に侵入、ゴルフクラブ41本(時価合計41万円相当)を盗んだ疑い。
調べに対し「昨年12月に建設関係の会社から派遣切りされ、路上生活をしていた。生活のため、ほかにも十数件やった」と供述しているということです。
盗んだクラブは、同市中村区のゴルフ用品店で1本1000〜3000円で売却、生活費に充てていました。逮捕時の所持金は4000円でした。
(3月17日読売新聞より抜粋)
派遣切りによる生活苦で窃盗や強盗・・というのが全国で増えています。
埼玉県では14日、乗用車を盗んだとして同県北本市二ツ家3、元派遣社員男(42)が逮捕されまし「派遣切りに遭い、自分で引っ越しの荷物を運ぼうと元同僚の車を狙った」と供述しているということです。解雇された会社近くのアパートから北本市内に引っ越し、「業者を頼む金もなかった」と話しています。
こういう素人がプロの領域に入ってきて犯罪を起こす事件が増えてくると、警察も従来の窃盗犯に加えて、その対応を行う必要が出てくるため検挙率も下がるのではないかと危惧します。
どちらにしても、今年は年間の窃盗犯や強盗の数は急増するのではないかと予想します。
多くの事業所や店舗、一般家庭が先の見えない不況のため財布の紐を固く閉じています。
しかし、一方で犯罪が急増、今回のように不況の影響で職を失った人が犯罪を起こすことになると、犯罪に遭遇する可能性も高くなります。
そして不幸にも窃盗被害に遭ってしまうと、その被害は保険だけでは対処できないことも多いのです。
たとえば金庫を破壊される、パソコンを盗まれる、ガラスを割られる、扉をこじ開けられる。商品・仕掛品・備品にいたずらされる・・・こうした被害全てに対応できる保険をかけておられる方は少ないです。
保険は保険目的として対象になるものをきちんと指定しないと対象にはなりません。
ですので、盗難保険に入っていたとしても対象にならないことは多いのです。
そんな対象にならない被害の場合、修繕費や購入費は自前です。
リースで購入したものでも、減価償却されリース残がリース動産総合保険の上限ですから新品を購入する費用にはなりません。やはり自前になります。
それにも加えてパソコンの中のデータは失う。顧客名簿など個人情報が入っていたら「個人情報漏洩」の加害者扱いになる。警察が調べる間は営業もできない・・。
それが窃盗被害に遭うということなのです。
この不況の中で、リスクは予防することが大切だと思いませんか?
「予防」こそが重要だと考えている防犯システムをお勧めします。
投稿者: スタッフ (2009年3月18日 15:08)