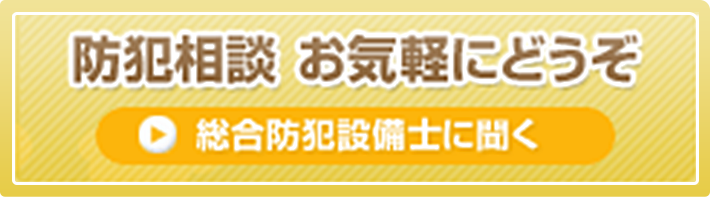今日巷で話題の犯罪について防犯のプロが語る
宅配ボックスに届いた他人の靴盗み、ネットで転売
マンションの宅配ボックスから荷物を盗んだとして、京都府警南署は31日、窃盗の疑いで、京都市南区にある市立小学校の非常勤講師の女(58)=同区=を逮捕した。容疑を認めているという。
逮捕容疑は3月16日午後1時50分ごろ、自宅マンションに設置された宅配ボックスから、住人の会社員男性(38)宛てに届いた革靴など2点(時価計約18万円相当)を盗んだとしている。
宅配ボックスは専用のカードをかざして解錠する仕組みで、男性は3月上旬にカードを紛失していた。女は「(男性の)カードを使って開けた」と供述しているという。
荷物が届かないことを不審に思い、スマートフォン向けフリマアプリ「メルカリ」での出品を疑った男性が、革靴がメルカリで売却されていることを確認。革靴の出品者の別の出品物を購入したところ、発送元から同じマンションの住人だと判明した。
<5/31(木) 23:11配信 産経新聞より>
マンションの宅配ボックス、私が住んでいるマンションについ先日導入されました。(ある夜帰ったら突然出現していたのでびっくりしました)
管理会社から暗証番号を記した書類が郵便ポストに入っており、まだ内容を確認していないので宅配ボックスの仕組み自体をよく理解していません。
想像になってしまいますが、マンションの住民が共有で使用できる宅配ボックスがあり、不在時等に配達の方がそこに預ける。
専用のカードを使用し、そのボックスを開けて荷物を受け取る。
住人の誰かもが勝手に持ち出すことができるボックスだと、悪意を持った住人が盗むことも考えられます。
配達の場合は、受け取った人にサインや捺印をしてもらいますので後で誰が受け取ったかということを追跡することができます。
宅配ボックスはそれができないと思うので、その場からなくなった場合はどうしようもないような気がします。
配達した運送会社にも責任がないでしょうから、そのシステム自体の問題ということになります。
宅配ボックスで防犯カメラが内蔵したものや指紋や虹彩認証で受け取った人の履歴が分かるようなものがあると人気が出るような気がします。
配達の方が再配達することもなくなりますので、今問題になっている運送会社の運賃問題も良い影響を与えるでしょう。
セキュリティ面がより強化され、配達する側にもメリットがあり、受け取る側にもメリットがあれば誰もが利益を受けることができる最良の仕組みとなります。
今発生している問題も今後の課題として役立たせることができれば決して無駄にはなりません。
投稿者: 総合防犯設備士 (2018年6月29日 20:11)
民泊用のマンションに侵入、性的暴行目的
東京・板橋区のマンションで観光客の女性を脅して性的暴行を加えようとしたとして、劇団員の男が警視庁に逮捕されました。
逮捕されたのは劇団員の男(31)で、今年1月、板橋区のマンションの部屋に侵入し、台湾から観光で来ていた10代の女性に対し、首にカッターナイフを突きつけて脅した上、性的暴行を加えようとした疑いが持たれています。
この部屋は民泊として使われていて、椎名容疑者は鍵のかかっていないドアから侵入したとみられています。
調べに対し、「刺激を求める癖があり、スリルやドキドキ感を味わいたかった」と容疑を認めているということです。(01日11:05)
<6/1(金) 13:31配信 TBS News iより>
訪日外国人が急増し、宿泊施設が不足しており、そこに民泊の需要が高まっています。
普段は使用していない部屋や空き家などが有効活用できることで、外国人側も日本人側もお互いにメリットがあるという良い一面はあります。
ただ、今回のような民泊で使われる部屋や施設の防犯対策が手薄な点を突いた犯罪も想定されます。
民泊用の施設や部屋が増えてくると、今度は利用者側の選ぶ権利が強くなります。
より安くて、より便利で、より安全で、より快適な施設に人気が集まることでしょう。
その中の安全に関しては、管理人や警備員が常駐しているという人的な面での対策や防犯カメラや非常用押しボタンなどの緊急通報などの機械での対策がより充実しているところが選ばれるでしょう。
民泊を検討している方がいればその点も考慮した方が今後は良いと思います。
投稿者: 総合防犯設備士 (2018年6月22日 16:08)
刑務所の高齢化進む 3食と寝場所も約束
全国の刑務所で高齢の受刑者の割合が増加している。
かつては犯罪を起こすのは分別のない若い世代で、家族を持ち、年齢を重ねるにつれて、反社会的行動はとりづらくなると考えられていた。
実際、30年前の1976年は受刑者の60歳以上比率は2.5%だった。
ところが、2017年版犯罪白書によると、全受刑者2万467人のうち60歳以上の受刑者は3750人で、全体の18.3%を占めている。
高齢受刑者の罪名別構成比は男女ともに窃盗がトップだが、特に、女子の場合88.4%と際立って高い。
生活苦から万引きを繰り返し、3食と寝る場所が保障された刑務所に舞い戻るために、出所後ほどなくして同じ罪を犯す高齢者も少なくないという。
刑務所が一種のセーフティネットになっているともいえる。
法務省は、2015年に実施した調査で、全国の60歳以上の受刑者のうち認知症傾向がある人が約1300人いると推計。
刑務官による生活介助や飲み込みやすいペースト食の準備など高齢受刑者の増加に伴う現場の負担も増えている。
2019年度から新たに刑務所に入る60歳以上の受刑者に対し、認知症の簡易検査を実施、認知症が疑われる場合には、医師の診察を受けさせる。
早期発見により治療の機会を確保し、出所後の社会復帰をしやすくするのが狙い。
<5/18(金) 11:07配信 nippon.comより>
ホームレスの人でも生きていくにはお金が掛かります。
自分の食べる物や生活に必要な物、これらを手にするにはお金を支払うか、配給のようなもので受け取るか、落ちているものを拾うか、最終的には人から奪うという手段を考える人がいるかもしれません。
このような大変な道に比べると、3食と寝る場所が保障され、なおかつお金が掛からない刑務所というのは天国のような場所だと考える人がいるのも当然です。
刑務所の中では労働や作業等が強制的に行わなければならないものもあるでしょうが、例えば日常的に暴力を振るわれたり、虐待されるようなことはないでしょうから、ホームレスに比べると安全で安心できる生活を送ることができます。
個人的にホームレスか刑務所かどちらか選ばなければならなければ刑務所を選ぶような気がします。
刑期を終えた後に社会復帰するつもりがあれば刑務所に入るということは大きなデメリットになりますが、ホームレスのように生きていくだけで精一杯という生活になれば人からどう見られようが関係ありません。
これから高齢化社会がさらに加速し、そしてAIの進歩などで働き口がさらになくなり、高齢者でそして貧しい人はホームレス、そして刑務所に入ることを目指す人が増えてくるかもしれません。
刑務所の高齢化もさらに進むでしょう。
医療の進歩も目覚ましいですから刑務所の中で長生きするという人も増えてくるでしょう。
ただ、万引きなどの軽い罪での服役の場合、刑期が短くなりますから、出所してさらに万引きし、また入所。
これが面倒になってくると、殺人などの重い罪を犯し、死ぬまで刑務所暮らしを覚悟するような者も出てくるかもしれません。
そうなると凶悪犯罪が増えてくることになります。
貧困者の援助や救済、出所後の社会復帰、そして刑務所内でのメンタルケアなど単に罰を重くするだけでは解決しない問題が今後の大きな課題ではないでしょうか。
投稿者: 総合防犯設備士 (2018年6月15日 11:12)
東京新宿 ホストクラブから高級酒盗まれる
ホストクラブから高級な酒を盗んだとして、警視庁新宿署は窃盗などの容疑で、静岡県焼津市大栄町の建設作業員の男(28)を逮捕した。
容疑を認めている。
逮捕容疑は4月12日午後、東京都新宿区歌舞伎町のホストクラブに侵入し、1本時価約34万円のブランデーなど、高級酒13本(同計約144万円)を盗んだとしている。
新宿署によると、石崎容疑者は盗んだ酒をスマートフォン向けのフリーマーケットアプリ「メルカリ」に出品し、コンビニエンスストアなどから発送。防犯カメラの画像などから関与が浮上した。
同署管内では今年に入り、飲食店の高級酒が狙われた同様の被害が数件相次いでおり、関連を調べている。
<5/14(月) 12:34配信 産経新聞より>
ホストクラブというのは泥棒にとって実は魅力的な対象なのかもしれません。
今回盗まれた高級酒もそうですが、その他にも多額の現金が置かれている可能性があります。
お客さんにもよるでしょうが、現金で支払う人も多いかもしれません。
従業員への給料も銀行振り込みではなく現金で支払っているところもまだあるかもしれません。(今時ないでしょうか・・・)
ホストクラブへの印象が古いかもしれませんが、現金のやり取りが多い場所というイメージがあります。
日々の売上金も他の飲食店に比べると多いと思いますので、自然に現金の保管額も多くなります。
毎日のように銀行に預けている店舗ではなく、数日間、もしくはそれ以上の現金を置いている場合はさらにリスクが高まります。
ホストクラブで防犯対策というのはあまりイメージにそぐわないかもしれませんが、侵入盗難対策だけでなく、お客さんとのこトラブル防止策としての防犯カメラ設置なども検討してはいかがでしょうか。
投稿者: 総合防犯設備士 (2018年6月 8日 17:14)
家の様子が筒抜け? IoTの意外な危険性
「セキュリティ」が大きな問題に
すでにオフィスや家庭にも幅広く活用され始めているIoTですが、実はいま、その危険性が問題視されています。特にIoTで大きな問題となっているのは「セキュリティ」です。
さまざまなモノがインターネットにつながっている状態でありながら、そのセキュリティ対策はまだ充分でなく、ハッキングなどを受けてしまう可能性があるというのです。実際に、あるカジノでIoTを搭載した「温度計」がハッキングされて、そこから店内のネットワークに侵入を許し、客の個人情報が盗まれたという事例が確認されています。
手軽なウェブカメラに潜む危険!?
あるいは、インターネット経由で家の中の様子を確認できる「ウェブカメラ」。仕事中や買い物中でもスマートフォンで家のペットや子どもの様子が確認でき、しかも安いものなら2000円弱からと、わりと気軽に買えることもあって人気があるのですが、これがハッキングされる被害も実際に出てきています。家の中がよく見えるように設置するものだけに、これが乗っ取られたりデータ通信が傍受されたりすると、それこそ家の様子が第三者に筒抜けになってしまいます。
IoTを利用したホームセキュリティの機器なども注目されている昨今ですが、上記のように機器自体の安全性もまた問われています。われわれの暮らしをより良く、便利にしてくれるのは間違いないIoT技術ですが、多少は高くてもセキュリティの高い製品を選ぶなど、われわれのほうも、関わり方をきちんと見直す必要があるかもしれません。
<5/11(金) 12:20配信 クロスメディア・パブリッシングより一部抜粋>
IoTという言葉はかなりメジャーになりました。
モノインターネットという説明までは、かなり多くの人が答えられるのではないでしょうか。
様々な家電製品がインターネットにつながっている状態になりますが、具体的に何がどのようにつながっているかを把握している人は少ないでしょうし、実際にそうすることは難しいでしょう。
また、どのような情報をどこに伝えているかとなると、もう人の力では管理できなくなります。
こうなると、その管理できないという状況を悪用し、そこから情報を引き出す、盗み出そうと考える犯罪者が必ず出てきます。
今後は、金品などを侵入にし盗もうとする泥棒などの犯罪者に対するセキュリティ(防犯対策)と、インターネット上の犯罪者に対する情報セキュリティ、そのどちらの対策も必須となります。
情報セキュリティに関しては、目には見えない対策ですので一般の人からするとその効果がさらに分かりにくいかもしれませんが、これだけパソコンやスマートフォンが普及し、インターネットが身近になりますと、無体策では被害に遭っていないことの方が不思議と言えるかもしれません。
便利であることの利点に対して、危険性も増加してしまうことはやむを得ないのかもしれません。
投稿者: 総合防犯設備士 (2018年6月 1日 18:46)