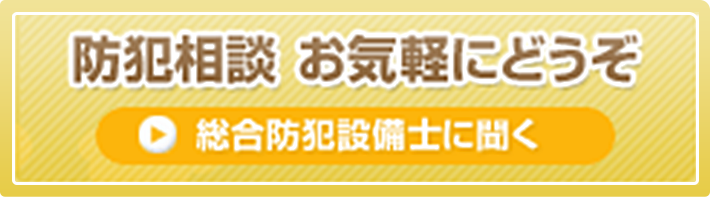今日巷で話題の犯罪について防犯のプロが語る
連続「緊縛強盗」 4府県で11件。
大阪や兵庫で「緊縛強盗」を繰り返していたとして逮捕された3人。
調べでは、男らは6月24日未明、大阪府吹田市の個室ビデオ店に押し入り、ナイフなどを突き付けて店長を脅し、粘着テープで緊縛。売上金など約26万円を奪った疑い。
3人は6月から7月にかけ、大阪、兵庫、京都、滋賀の4府県で、個室ビデオ店やコンビニエンストアを狙い、同様の手口で計11件の犯行を重ねていたとみられています。
「緊縛強盗」とは粘着テープ等で縛るなど被害者の自由を奪った上で、犯人自ら金品を探し取り出すものをいいます。
強盗 とどう違うのか?と思うのですが、「緊縛は被害者の身体を理不尽に拘束する行為のため、窃盗罪に監禁罪がプラスされる。縛る途上で傷でも負わせれば傷害罪がプラスされる。また盗んだものの賠償だけでなく、慰謝料も請求される。いずれにしろ罪は重い。」といった違いがあるようです。
そう解説されると、「ううん、なるほど」と思いますが、被害者にとっては命が危険にさらされる事態です。
うかつに逆らうと本当に大怪我をしたり、殺されたり・・といったこともあります。
一時期「キンコキンコ強盗」などといった見出しでよく新聞に出ていました。
一般家庭に強盗に入り、「キンコ キンコ」とか「カネ カネ」といった単語だけを発して、家族をガムテープで縛り、金庫から現金を盗むという外国人窃盗団が暗躍していました。
侵入強盗 は平成15年には平成9年の2.9倍になるなど急増しましたが、それ以降平成18年まで減少しています。しかしそれでも平成9年の1.9倍ですから、まだまだ多発しているといえます。
商店が 49.3%、一戸建て住宅が 12.1%、4階建て以上の共同住宅 8.3%、3階以下の共同住宅 8.3%、金融機関 9.9%となっています。
なんか金融機関が中心の犯罪のように思いますが、ここでも犯人にとっての「容易性・安全性・確実性」を追求するということなのでしょう。
つまり、防犯 対策・強盗 対策のとられている金融機関より商店や住宅の方が金額は少なくとも容易に、安全に犯行ができるという判断なのだと思われます。「ハイリスク・ハイリターン」ではなく「ローリスク・ローリターン」ということでしょうか。
ちなみに、犯行発生時間帯は午前2時〜午前4時が最も多いです。
やはり深夜の店舗が狙われているのです。
強盗に関しては単独犯が多いのですが、青少年が数名でといった犯罪もあります。
防犯 対策としては、
1)緊急通報システムを採用。ペンダント・腕時計・カードなど無線タイプの非常押しボタンを使用し、強盗時に気付かれず離れた場所に異常発生を連絡する。
2)防犯 監視カメラを店の出入口に向けて設置、犯罪者に対し、精神的に抑止するとともに録画する。
3)「強盗 対策実施中」などのプレートや「警戒中」の防犯灯などで、防犯・警備システムが完備していることを建物の外で示す。下見の犯罪者にアピールする。
4)店舗の構造を内外の死角をなくし視認性を高めるとともに、駐車場など店舗周辺に向けた防犯 カメラ設置に努める。最終退出出口の外にも防犯 監視カメラを設置し、外に待ち伏せされていないか確認してから外に出る。
5)防犯 責任者を選定し、防犯 設備の点検・整備、従業員に対する防犯 指導と防犯 訓練の実施、110番通報マニュアルの備え付け等任務を遂行する。
6)深夜時間帯の従業員の複数配置する。
7)レジ内現金の自主管理。投下式金庫活用。レジ内は3万円以下にする。
8)強盗 対策用カラーボール、アレストスプレー、ネットガード、防刀楯等を設置する。
9)防犯 カメラの死角をなくし定期点検・整備する。
10)ATM機はカウンターからの監視や防犯 カメラによる監視が可能な場所に設置する。
一般家庭の場合には
1)必ず相手を確認し、知っている人でない場合にはドアチェーンをつけたまま対応するか、インターホンで対応し、扉を簡単に開けない。
2)子供や女性一人だけの時には扉を開けないようにする。
3)宅配便などを装ったり、上階の住民を装ってということもあり注意する。
4)帰宅途中から後をつけられて扉を開けた瞬間に強盗されることもあるため、常に後ろにも気を配る。
5)一人暮らしの場合には一人であることをカムフラージュする。(カーテンの色、洗濯物、表札、玄関の靴など)
投稿者: スタッフ (2007年8月 7日 09:34)