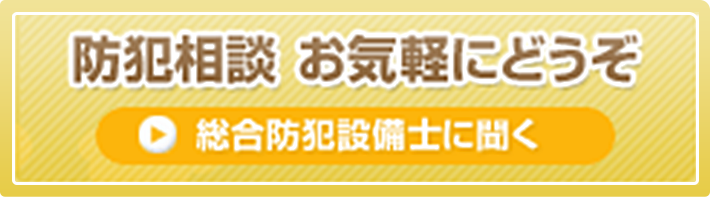今日巷で話題の犯罪について防犯のプロが語る
氾濫する暗証番号・パスワード
訪問介護先の女性宅から盗んだ通帳を使って現金を引き出したとして、和歌山北署は7日、有印私文書偽造・同行使と詐欺の疑いで、かつらぎ町丁ノ町の元介護士の男(49)=窃盗罪で起訴=を再逮捕しました。
容疑を認めているという。
再逮捕容疑は3月11日、訪問介護先の女性宅から盗んだ通帳を用い、偽造した払戻請求書とともに、和歌山市内の金融機関窓口で現金189万円を引き出したとしています。
通帳の口座からは複数回にわたり計1千万円が引き出された形跡があり、同署は男が関与したとみて調べています。
<産経新聞5月8日(水)7時55分配信より>
介護士やヘルパーが訪問先で窃盗を行ったり、通帳やキャッシュカードを持ち出し不正に現金を引き出すなどの事件がよくニュースになります。
これらの防犯対策は個別に行う必要がありますが、それとは別に、一つ疑問に感じることがあります。
キャッシュカードが盗まれた後、どのようにしてコンビニや銀行から現金が引き出されているのでしょうか。
プロの泥棒や犯罪者が特殊な機器を用いて暗証番号を読み取る、解析するというのは分かりますが、今回の事件のような、どちらかというと衝動的な犯行においても、現金の引き出しに成功しています。
おそらく暗証番号が容易に推測できる番号なのでしょう。
生年月日や住所の番地、電話番号など、いくつか推測できる番号を試して、最終的に暗証番号を特定しているのでしょう。
また、通帳やカードと一緒に暗証番号を書いたメモなどを置いており、そこから簡単に暗証番号が知られているということもあるでしょう。
金融機関のATMを利用する際、毎回しつこいと感じるほどに、暗証番号は問題ありませんか?というメッセージが流れます。
これは盗難時、不正引き出しを防止するための金融機関からの注意・警告です。
きちんと意味のある取り組みだと分かります。
ただ、簡単に推測できない番号を覚え続けることはなかなかできません。
また、複数のキャッシュカードを持つ場合、同じ暗証番号で良いのかという問題もあります。
さらに、他にインターネット上でIDやパスワードを登録することも多々あります。
これらのパスワードと混同してしまわないようにもしなければなりません。
パスワードを一括管理するソフトやインターネット上のサービスもあると聞きますが、パソコンやスマートフォンが壊れたり、紛失した時、そのサイトに辿り着くかという心配もありますし、セキュリティ(インターネットセキュリティ)の問題も心配です。
非常に覚えやすく、そして人からは分かりにくい、なおかつ忘れた時もすぐに分かるという万能な暗証番号・パスワードといいうものがあればいいのですが。
指紋や虹彩など生体認証でその個人だとほぼ100%特定できるシステムが金融機関やインターネットの世界でも広がれば、面倒なことをしなくてもよくなります。
近未来を描いた映画のように、そのような時代がいつか来るでしょう。
投稿者: 総合防犯設備士 (2013年5月 9日 13:35)